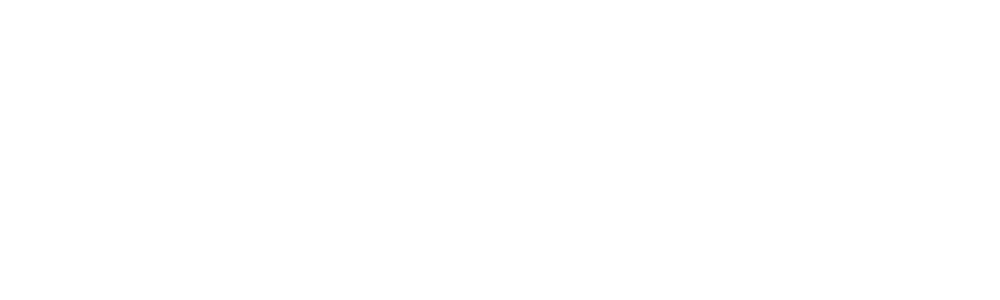「プログラミングに興味はあるけど、費用はなるべくかけたくない」「続けられるか分からないから、まずは無料で試したい」──そんなご家庭は多いのではないでしょうか?
この記事では、小学生が無料で安心して始められるプログラミングの方法・サービス・教材を、国内でもっとも詳しく紹介します。必要な機材、保護者のサポートポイント、よくある疑問にも丁寧に答えていきます。
目次
必要なものは?事前に知っておきたい環境準備
パソコン or タブレット
基本的にはノートパソコン(WindowsまたはMac)推奨。iPadやChromebookでも対応可能な教材もあります。スマホだけでは操作性がやや難しいため、なるべく画面の大きい端末を準備しましょう。
インターネット環境
Scratchやcode.orgなど、多くの教材はブラウザを使って学習するため、安定したWi-Fi接続が必要です。
メールアドレス(保護者用)
アカウント登録が必要な場合に使用。Googleアカウントがあると便利です。
無料で使える人気教材5選
Scratch(スクラッチ)
- 【対象年齢】小学校低学年〜
- 【特徴】MITが開発した世界標準の子ども向けプログラミングツール。
- 【メリット】ブロックを組み合わせるだけで、ゲームやアニメが簡単に作れる。日本語対応&操作直感的。
- 【推奨】まず最初の1本に最適。
- https://scratch.mit.edu/
code.org
- 【対象年齢】5歳〜高校生
- 【特徴】ステージ制の学習で、パズル感覚でプログラミングの概念を理解できる。
- 【メリット】初心者が一人でも進めやすい。ディズニーやマインクラフトとのコラボ教材も人気。
- https://code.org/
プログラミン(文部科学省)
- 【対象年齢】小学生〜中学生
- 【特徴】日本の文部科学省が監修した安心の教材。
- 【メリット】ブラウザ上で動作し、操作が簡単。ローカル保存不要。
- https://www.mext.go.jp/programin/
Viscuit(ビスケット)
- 【対象年齢】幼児〜小学生低学年
- 【特徴】絵を描いてプログラムを作る独特のスタイル。
- 【メリット】文字が読めない年齢の子も使いやすい。直感的でアート的。
- https://www.viscuit.com/
MakeCode(マイクロソフト)
- 【対象年齢】小3〜
- 【特徴】マイクロビットやロボット教材との連携も可能。
- 【メリット】Scratchより少し本格的。ハードウェア連携も無料で体験可。
- https://makecode.microbit.org/
無料で学べるYouTubeチャンネル・教材サイト
YouTubeチャンネル
- たのしいスクラッチ講座(日本語):Scratchの基礎からゲーム制作まで網羅。
- Tech Kids School チャンネル:子ども向けオンラインスクールの一部内容を無料で公開。
- SEIKAI プログラミングキッズ:小学生向けの図解つき解説が豊富。
サイト例
- すてむぼっくす(STEMBOX):プログラミングだけでなく、理科や算数との連携学習も。
- こどもプログラミング広場:無料ワークショップ情報や教材ダウンロードが可能。
自宅での学習の進め方(スケジュール例)
ステップ1:Scratchで「キャラを動かす」
- 週1〜2回、30分〜60分が目安
- 完成物が見えるので達成感あり
ステップ2:作品発表をしてみよう
- 家族に見せる、動画に撮る、SNS投稿も◎
- 自己表現とモチベーションUPに繋がる
ステップ3:教材を組み合わせる
- Scratch + code.orgや、Viscuitと並行学習
- アニメ制作、音楽制作など方向性を広げる
保護者ができるサポート
- 「一緒にやってみよう」の姿勢が◎
- 声かけ例:「すごい!どうやって動かしたの?」「工夫したところはどこ?」
- 完成品を飾る・録画する・記録する=達成感UP
よくある質問
Q. 無料教材だけで十分ですか?
A. 初期段階では十分です。続けて本格的に学びたくなったら、有料スクールや教材にステップアップするのもOKです。
Q. パソコンがない場合は?
A. タブレットでも一部教材は利用可能ですが、画面の大きさや操作性の点でパソコンの方が快適です。中古PCやChromebookも選択肢です。
Q. ゲームばかりになりませんか?
A. 「つくるゲーム」と「遊ぶゲーム」は別物です。制作体験を通じて、受け身の姿勢から主体的な学びへ変化していきます。
まとめ
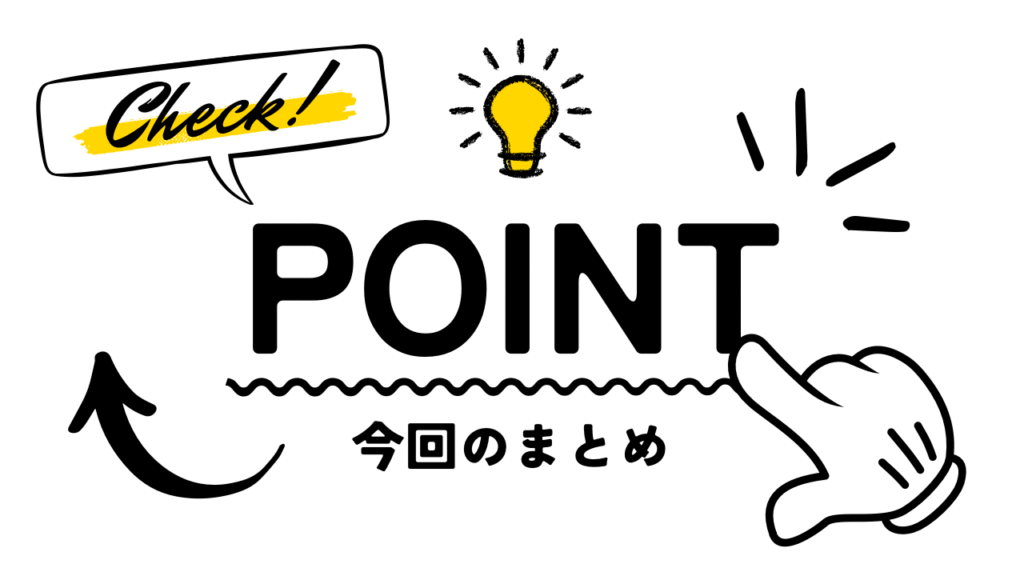
プログラミングは、「将来のため」に始めるだけでなく、「今、楽しいから」でも十分価値があります。特に無料教材の充実した今は、親子で気軽にスタートできる最高のタイミングです。
最初の一歩は、「クリックして動かす」だけでOK。そこから、自分のアイデアが形になる楽しさを、ぜひお子さんと一緒に体験してください!