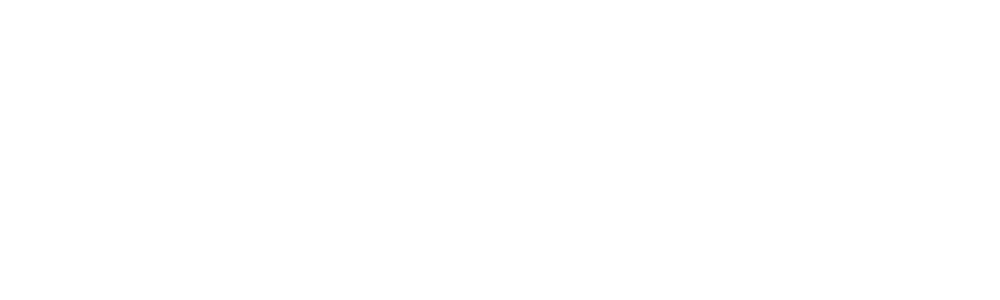「プログラミングって、最近よく聞くけど…うちの子にも必要?」
「私が教えられないのに、どうやって始めればいいの?」
そんな疑問や不安を抱えた親御さんへ。
いま、小学6年生というタイミングは、子どもが“考える力”を伸ばし、将来の選択肢を広げるための絶好のチャンスです。
本記事では、
- なぜ今プログラミングが注目されているのか
- 小学生が無理なく学べる方法やおすすめ教材
- 親が知っておきたいサポートのポイント
などを、未経験の親でも安心して読めるよう、わかりやすくまとめました。
将来の力になる学びを、いま親子で一緒に楽しんでみませんか?
それでは早速、プログラミング学習の基本から見ていきましょう!
なぜ今、プログラミングが必要?
プログラミングは一部の専門家だけが扱う特別な技術と考えられていました。
しかし、現代社会ではAIやロボット技術の進化により、プログラミングは誰もが理解し活用できる「新しい読み書き」として注目されています。2020年からは小学校でプログラミング教育が必修化され、2025年以降は大学入試にも関連科目が導入される予定です。
プログラミングを学ぶことで、子どもたちは単にパソコンの操作方法を覚えるだけでなく、論理的に考える力や問題を解決する力、創造的な発想、そして失敗から学ぶ姿勢など、これからの社会で必要とされる多くの能力を自然と身につけることができます。
特に小学6年生は、自分で考え行動する力が育つ大切な時期です。中学校への進学を控え、自ら学ぶ姿勢を養うためにも、プログラミングは非常に有効な学びの一歩となるでしょう。
プログラミング教育の基本と制度
日本の小学校では、2020年度からプログラミング教育が正式にカリキュラムに導入されました。これは国語や算数のような「教科」ではなく、「教科横断的な活動」として位置づけられています。たとえば、算数の「正多角形の作図」をプログラムで行ったり、理科の「電気のはたらき」をロボット制御を通して学んだりします。
つまり、小学校でのプログラミング教育の目的は、「コードを書く技術」を教えることではなく、「プログラミング的思考」を育てることです。
この考え方は中学校・高校と進むごとに徐々に実践的な技術に移行していきます。中学校では「技術家庭科」の中でプログラムを実際に作る授業が行われ、高校では「情報Ⅰ」が共通必修科目として登場します。
制度的にも、文部科学省は「情報教育の体系化」に向けて動いており、将来的には大学入試や就職試験で、プログラミング力やITリテラシーを問われる時代が到来するでしょう。小学生のうちから少しずつでも触れておくことで、大きなアドバンテージになるのです。
小学生におすすめの学習方法
では、実際に小学生がどのようにプログラミングを学べばよいのでしょうか。代表的な方法は次の3つです。
1. ビジュアル型プログラミング(例:Scratch)
ScratchはMITが開発した子ども向けの無料プログラミングツールです。ブロックをドラッグ&ドロップして組み合わせることで、ゲームやアニメーションが作れます。小学6年生でも直感的に扱えるため、最初の一歩に最適です。
2. ロボット・IoT教材(例:micro:bit, LEGO SPIKE)
ハードウェアを使ったプログラミングも人気です。たとえばmicro:bitでは、自分の作ったプログラムでLEDを光らせたり、音を鳴らしたりできます。触って動くものがあると、子どもたちの関心も持続しやすいです。
3. オンライン学習教材・スクール
最近はオンラインでも高品質なプログラミング教材が多数登場しています。動画で学べる「Progate for Kids」、ゲーム形式の「コードモンキー」など、家庭での学習にピッタリです。
学習のポイント
- ゲームを作らせること:目に見える成果があるとやる気が続く
- 短時間×定期的:毎日10分でもOK。継続がカギ
- アウトプット重視:作ったものを家族に発表させると、表現力もUP
親が知っておきたいサポート術
親がプログラミング未経験でも、子どもをサポートすることは十分可能です。以下の3つの姿勢が重要です。
1.「わからない」を一緒に楽しむ姿勢
子どもが「これどうやるの?」と聞いてきたら、「一緒に調べてみよう」と言うだけで十分です。大切なのは「親も一緒に楽しんでいる」雰囲気をつくること。
2. 成果ではなく過程を褒める
「うまく動かなかったけど、何度も試したんだね」「エラーを自分で直せたんだね」といった声かけが、子どもの自信を育てます。
3. スクリーンタイムの管理
「ゲームとプログラミングの境界」が曖昧になりがちです。明確に「これは学びの時間」と区切り、時間を決めて行うことが大切です。
また、定期的に「何が楽しい?」「どんなものを作りたい?」といった質問を投げかけることで、子ども自身の内発的動機も育てられます。
体験談・インタビュー記事
「実際にやらせてみたらどうだった?」「他の家庭はどう始めたの?」
そんな疑問に応えるのが、リアルな保護者や子どもの体験談やインタビュー記事です。
スクールを選ぶときの決め手、家庭学習で工夫したこと、途中でつまずいたエピソード、そして“できた!”と笑顔になった瞬間まで、実際の声からは教材の使いやすさや学びの効果が見えてきます。
ケース1:Scratchで“迷路ゲーム”を作った小学6年生
「最初はぜんぜん動かなくてイライラしたけど、YouTubeを見ながら直したら動いたとき、めっちゃうれしかった!」
この男の子はもともとゲーム好き。親が「ゲーム作ってみたら?」と声をかけたことで、興味が芽生えたそうです。今では「将来はゲームクリエイターになりたい」と夢を語っています。
ケース2:プログラミング未経験の母と息子で一緒に学習
「最初は怖かったけど、ブロックをつなげるだけで動くとわかって楽しかった」と語るのは小学5年生の女の子。母親は「勉強っぽくないからか、毎日続けていて驚きです」と語ります。
親子で一緒に学ぶ姿勢が、自然な学びの習慣を生み出していました。
おすすめ教材・サービス紹介
cratchを使った無料サイトや、タブレット学習、ロボット連携キット、本格アプリ開発まで、今は“遊びながら学べる”時代。費用・レベル・楽しさのバランスが取れた教材を選べば、自然と「やってみたい!」が芽生えます。
無料で始めたい方向け
- Scratch(スクラッチ):ビジュアル型プログラミングの定番
- Code.org:ステージ制でゲーム感覚で学べる
本格派・教材を使いたい方向け
- micro:bit:ハードウェアを使って学ぶ
- レゴ SPIKE:動きのあるプログラミング体験が可能
- QUREO(キュレオ):小学生向けに特化した教室型
比較表の一例(抜粋)
| 教材名 | 対象 | 特徴 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| Scratch | 小1〜 | 無料・直感的 | 無料 |
| QUREO | 小3〜 | 教室形式で安心 | 月額9,000円前後 |
| micro:bit | 小4〜 | 実物を使って学べる | 初期費用2,000円〜 |
おすすめの本
ゲーム作りで楽しみながら学べるScratch本、アプリ開発やロボット教材まで挑戦できる応用書、さらには紙と鉛筆で思考力を鍛える“アンプラグド教材”まで、子どもの興味やレベルに応じた多彩な本がそろっています。
おすすめのスクール
Scratchやロボット、マインクラフト、アプリ開発など、子どもたちの興味を引き出す多彩なカリキュラムがそろい、講師のサポートや仲間との交流で“学ぶ楽しさ”もアップ。
オンラインスクール
Scratchやマイクラ、ロボット、アプリ開発など、楽しみながら本格的に学べるカリキュラムがそろっていて、講師のサポートや映像教材で“はじめて”でも安心。移動不要で、全国どこからでも受講できるのも大きな魅力です。
教室
Scratchやロボット、ゲーム制作からPythonやアプリ開発まで、多彩なカリキュラムと実践重視の学びで、子どもの“やりたい!”を引き出してくれます。対面だからこそ得られる集中力・協調性・発表力も、これからの時代に欠かせない力。
よくある質問・お悩み相談
Q. 途中で飽きてしまわないか心配です…
A. 興味のあるジャンル(ゲーム、音楽、ロボット)を選ぶことがカギです。成果物を家族に披露するなど、小さな目標を持たせると効果的です。
Q. プログラミングって何の役に立つの?
A. 単にコードを書く技術ではなく、「論理的思考力」「問題解決力」「創造力」を育む教育として注目されています。将来どんな職業についても役立つ“考え方”が養われます。
Q. どのくらいの年齢から始めるのがいい?
A. 一般的には小学校低学年から始められます。早ければ年長さんから楽しめる教材もありますが、無理なく遊びながら取り組める時期にスタートするのがベストです。
Q. どんな教材やアプリがオススメ?
A. 初心者には以下のようなツールが人気です:
- Scratch(スクラッチ):ゲームやアニメーションを作れる
- Viscuit(ビスケット):もっと低年齢向けの直感的な操作
- マインクラフト教育版:楽しみながら論理力が育つ
Q. 家にパソコンがないけど大丈夫?
A. タブレットやスマホでも学べる教材があります。ただし、パソコンがあるとより幅広い内容に対応できますので、学習が進むにつれて準備を検討しても良いでしょう。
Q. 子どもがゲームばかりしていて心配…プログラミングに役立つ?
A. 「遊ぶ側から作る側へ」視点を変えるきっかけになります。ゲームを作ることでゲームへの理解が深まり、遊び方にも変化が出る子が多いです。
Q. 将来の進路にどうつながる?
A. ITエンジニアだけでなく、AI、ロボット、デザイン、マーケティングなど幅広い職業でプログラミング的思考が求められます。中高大の進学にも情報科目の重要性が高まっています。
Q. 塾や教室に通わせるべき?
A. 自宅でも学べますが、モチベーションの維持や継続的な学びには教室の活用も効果的です。まずは体験教室で雰囲気を見るのがオススメです。
Q9. 費用はどれくらいかかるの?
A. 教室によって違いますが、月謝は5,000〜15,000円ほどが一般的です。自宅学習の場合は無料教材も多く、初期費用を抑えて始めることが可能です。
Q10. 親はパソコンに詳しくないけど、サポートできる?
A. 専門的な知識がなくても大丈夫です。大切なのは「応援する姿勢」です。子どもの作品を一緒に見たり、感想を伝えたりするだけでもモチベーションが上がります。
まとめ
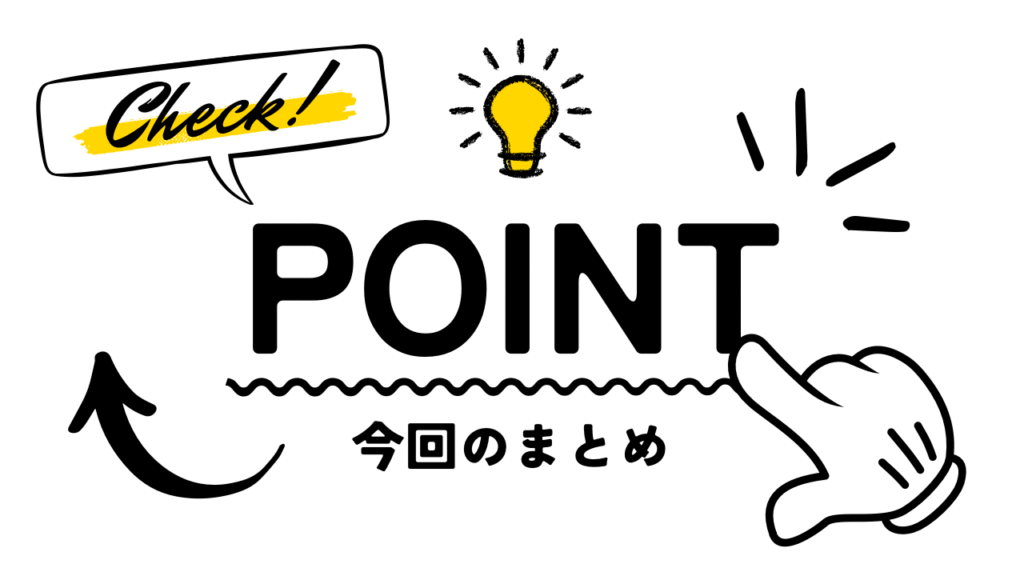
小学生からのプログラミング学習は、「将来に役立つスキルを育てる」だけでなく、親子の関係を深める学びのチャンスにもなります。ゲーム感覚で始められ、失敗から学び、創造的な力を育てる。そんな“今こそやるべき学び”として、ぜひ親子で一歩を踏み出してみてください。